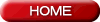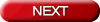福島県 福島県 |
 |
|
 |
||
| 天鏡閣 福島県耶麻郡猪苗代町翁沢字御殿山106-14 明治40年(1907)8月、有栖川宮威仁親王殿下が東北地方を御旅行中猪苗代湖畔を巡遊され、その美しさを賞せられてこの地に別邸を建設することを決定しまし た。 明治41年8月に竣工し、翌9月、皇太子嘉仁親王殿下(大正天皇)の行啓の際、同御別邸を「天鏡閣」と命名されました。 威仁親王薨去後、高松宮の所有 となり、第二次世界大戦後の昭和27年(1952)に、高松宮から福島県に払い下げられました。 |
||
 |
 |
 |
| 本館 | 別館 | 表門 |
| 木造二階建、スレート及び鉄板葺、正面車寄及び 八角塔屋付の建築面積491.9㎡の建物です。 ルネッサンス風の様式で、気品のある、洗練され た意匠をもっています。 |
木造二階建、スレート葺、建築面積99.2㎡の建物 です。 |
煉瓦造、左右袖塀付の柱門です。 |
 |
||
| 旧高松宮翁島別邸 福島県耶麻郡猪苗代町翁沢字畑田1072-4 旧高松宮翁島別邸は大正天皇第三皇子・高松宮宣仁親王殿下が、有栖川宮威仁親王妃慰子殿下の保養のために大正11年(1922)に建設されたものです。 当時、既に天鏡閣はありました自然の景観を庭園に見立てた純日本風のたたずまいを有する別邸を1年余りの歳月をかけて完成させました。 その後は、天鏡 閣と共に離れの日本間として、昭和天皇・今上天皇をはじめ多くの皇族を迎え入れ皇室歴史に深く関わっています。 昭和27年(1952)旧高松宮翁島別邸は天 鏡閣と共に高松宮殿下より福島県に御下賜され、福島県迎賓館として今日に至っています。 |
||
 |
 |
 |
| 玄関棟 | 居間棟 | 台所棟 |
| 大正11年(1922)に建設された木造、銅板葺建築 面積155.3㎡の建物です。 事務部門及び接客 のための空間で、檜の良材を随所に用い、釘隠し に意を凝らすなど質も高く和風の意匠でつくられた 大正期の皇族用別邸の一典型です。 |
大正11年(1922)に建設された木造、銅板葺、建 築面積254.7㎡の建物です。 居住用の空間で 玄関棟の裏側に隣接しています。 |
大正11年(1922)に建設された木造、銅板葺、建 築面積179.7㎡の建物です。 使用人のための 空間で玄関棟の右側に隣接しています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 旧正宗寺 三匝堂(会津さざえ堂) 福島県会津若松市一箕町八幡字弁天下 甲1404-2 |
旧滝沢本陣横山家住宅 主屋 福島県会津若松市一箕町八幡滝沢122 |
旧滝沢本陣横山家住宅 座敷 福島県会津若松市一箕町八幡滝沢122 |
| 寛政8年(1796)に建立された、六稜三層形式向拝 付銅版葺の建物です。 高さ16.5mで、初層真径 約6.3mの六角形平面に回縁を付け、正面には唐 破風の向拝を付しています。 正面から入ると右回 りに螺旋状のスロープで登り、頂上の太鼓橋を越え ると降りの左回りのスロープとなって背面出口に通 じています。 昇降を通じて建物内を三度回ること から三匝堂の名があります。 スロープの内側に沿 って西国札所の三十三観音が祀られ巡礼を終えた ことになります。 |
横山家は古くから近郷十一ヵ村の郷頭でしたが、後に旧白河街道の本陣を兼ねるようになりました。 滝沢本 陣は、旧若松城下から白河、江戸に至る旧白河街道沿いにあり、会津藩主が白河街道を通る際の休息所と して使用されました。 |
|
| 主屋は建物は延宝6年(1678)に建造された桁行20 .1m、梁間7.6m、裏面切妻造、西面寄棟造、茅 葺、南面玄関附属の建物です。 屋内の半分が土間 となっているなど、近世の農民住宅の形がよく残され ています。 |
本陣座敷は19世紀初めに建て替えられたもので、 桁行10.5m、梁間7.4m、寄棟造、茅葺、西北隅 が主屋に接続している建物です。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 恵隆寺 観音堂 福島県大沼郡会津坂下町 搭寺字松原2944 |
旧五十嵐家住宅 福島県大沼郡会津坂下町 搭寺字大門1466 |
常福寺 薬師堂 福島県大沼郡会津美里町 新屋敷字山王塚甲99 |
| 恵隆寺は欽明天皇元年(540)が始まりと言われ る真言宗豊山派のお寺です。 観音堂は鎌倉時 代の建久年間(1190~1199)の建立といわれる、 桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、向拝一間、 茅葺の建物です。 会津ころり三観音霊場 会津三十三観音三十一番札所(立木観音) |
享保14年(1729)に建てられた、桁行16.3m、 梁間8.0m、寄棟造、茅葺、面積117.19㎡ の建物です。 直屋の、江戸時代中期、会津平 坦部の中堅層農家(本百姓)住宅の典型的な家 構えです。 |
建久8年(1197)、田子道宥の開山と伝えられるこ とから「田子薬師堂」とも呼ばれています。 桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、銅板葺の 建物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 成法寺 観音堂 福島県南会津郡只見町梁取字仏地1864 |
旧五十嵐家住宅 福島県南会津郡只見町叶津字居平437 |
中ノ沢観音堂 福島県南会津郡下郷町中妻字観音前228 |
| 成法寺は平安時代初期に創建された曹洞宗のお 寺です。 観音堂は室町後期の1504年~1520年頃に建 立されたと推定される御堂で桁行三間、梁間三間 、一重、寄棟造、茅葺の純唐様建築です。 御蔵入三十三観音第一番札所 |
五十嵐家は江戸中期の享保3年(1718)に建てら れた桁行13.3m、梁間7.6m、寄棟造、北面葺 きおろし下屋、南面突出部附属、茅葺の建物です。 江戸時代農村の中型層をなす本百姓でした。 建 物は現在中型の中門造になっていますが、最初は 直屋でした。 |
中ノ沢観音堂は大同2年(807)の創建と伝えられて います。 その後、正光寺、光明寺に属し昭和28年 から旭田寺となりましが、現在は観音堂を残すのみ です。 観音堂は嘉慶2年(1388)頃の建立と思わ れる、桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造、茅葺形 銅板葺の建物です。 基礎や仏像に火事の痕跡が ある為、平安時代に建てられた御堂が室町時代初 期に火災で焼失し、ほぼ同型の建物が再建された と推定されています。 御蔵入三十三観音第十一番札所 |
 |
||
 |
 |
 |
| 桙衝神社 本殿 福島県須賀川市桙衝字亀居山97-1 |
法用寺 観音堂 福島県大沼郡会津美里町雀林 字三番山下3554 |
法用寺 三重塔 福島県大沼郡会津美里町雀林 字三番山下3554 |
| 桙衝神社は養老2年(712)に創建された、延喜式 神明帳に記されている式内社です。 本殿は慶安元年(1648)に白河藩主榊原忠次の命 により再建されたもので、桁行三間、梁間三間、切 妻の流造、木羽葺の三間社です。 拝殿・随身門・神楽殿-須賀川市指定文化財 |
法用寺は養老4年(720)に創建された天台宗のお寺です。 会津坂下町の恵隆寺に次いで、会津で二番 目に古い寺院会津で会津三十三観音の29番札所にもなっており「雀林観音」と呼ばれています。 「仏都 会津」発祥の寺院として、会津の仏教文化を色濃く残す仏像等多くの文化財を保有している寺院です。 虎の尾ザクラ-市天然記念物 |
|
| 明和5年(1768)に建立された宝形造、銅版葺、方 五間、面積151㎡の建物です。 近世の観音堂で は県内最大のものです。 |
会津に現存する唯一の塔です。 安永9年(1780 )に建立された木造、三層宝形造、銅版葺、方三 間、全高19mの建物です。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 旧五十島家住宅 福島県大沼郡金山町中川字上居平949-1 |
旧長谷部家住宅 福島県南会津郡只見町叶津字居平456 |
旧南会津郡役所 福島県南会津郡南会津町 田島字丸山甲4681 |
| 18世紀半ば以前に建てられた農家建築です。 会津地方で見られる厩中門造り、茅葺の建物で、 桁行き9間、梁間3.5間の直屋部分に、桁行き2 .5間、梁間2.5間の厩中門が付けられています 。 直屋の主屋に張出すように厩が取り付けられ、 平面がL型のようになっています。 秋田地方を源 流とする日本海側東北地方一帯に広がる多雪対 応型の建物で、中門にウマヤと便所を設け、その 前面に入口をつけた形式です。 |
長谷部家住宅は会津藩と越後藩の境にあり、通行 人や物資の出入りを監視していた会津藩役人が待 機していた建物(御番所)です。 江戸時代後期に 建てられたと推測される桁行14.35m、梁間10. 15m、うまや中門付、寄棟造、茅葺の建物で、規 模の大きい上層家屋の曲り家です。 |
旧南会津郡役所は明治18年(1885)に建築された 木道二階建、亜鉛引鉄板葺。ベランダ・ポーチ付、 中庭式の建物です。 この頃は、本格的な洋風木 造が活発になった時期で、あいついで新改築された 県内十余か所の同庁舎のうちでは、北会津郡役所 に次いで規模が大きい建物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 旧猪股家住宅 福島県南会津郡南会津町 糸沢字西沢山3692-20 奥会津博物館 |
旧山内家住宅 福島県南会津郡南会津町界字川久保552 奥会津南郷民族館 |
白河ハリストス正教会聖堂 福島県白河市愛宕町50 |
| 18世紀前半頃に建てられたと推定される間口14. 32m、奥行6.69m、寄棟造、茅葺の建物です。 内部は畳を敷ける板敷の部分が二間だけで、残り は全て土座という、住居より作業場としての比重が 大きかったことを示す建物です。 旧山王茶屋-南会津町指定文化財 |
山内家は鴇巣の名主で上層農民です。 この建物 は18世紀後半建てられたと推定される桁行23.0 7m、間口14.梁行8.64m、下屋を含めて平面積 209.86㎡の直家です。 会津地方には例の少な い内縁を備えています。 旧斎藤家住宅-南会津町指定文化財 |
大正4年(1915)に竣工された木造平屋建て、一部 二階建て(鐘塔)、間口8.17m、奥行14.44m、 面積101m2の建物です。 ハリストス協会として現 存するものでは全国で5番目に古い洋風建築です。 全体は十字型平面で、屋根は切妻造や八稜屋根、 中央の聖所には方形屋根を二段にかけています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 桙衝神社 随身門 福島県須賀川市桙衝字亀居山97-1 |
桙衝神社 拝殿 福島県須賀川市桙衝字亀居山97-1 |
桙衝神社 神楽殿 福島県須賀川市桙衝字亀居山97-1 |
| 桙衝神社は養老2年(712)に創建された、延喜式神明帳に記されている式内社です。 日本武尊が御東征の折、この神民山(亀居山)に柊の八尋の矛をつきたて 武甕槌神を祀ったのが神社草創の初めという言い伝えもあります。 岩瀬郡の総鎮守として代々領主の信仰があつく、神域45ha、一の鳥居随神門より中世建築の 本殿を拝しています。 本殿-福島県指定重要文化財 |
||
| 随身門は享和元年(1801)に建立された、三間一 戸の八脚単層門です。 |
拝殿は享和元年(1801)に建立された、入母屋、唐 破風向拝付の建物です。 |
拝殿は享和元年(1801)に建立された、入母屋、鉄 板葺、妻入の建物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 護真寺 本堂 福島県須賀川市横田字北の後158 |
長楽寺 山門 福島県須賀川市桙衝字宮本172 |
善龍寺の山門 福島県会津若松市北青木13-32 |
| 護真寺は観応2年(1351)に開山された臨済宗の お寺です。 本堂は享保年間(1716~36)に建立さ れた寄棟、金属板葺、桁行8間、梁間6間の建物で す。 サクラ-福島県指定天然記念物 |
寛保2年(1742)に建造された切妻、石瓦葺き、一 間一戸の四脚門です。 |
善龍寺は寛永20年(1643)に建立された曹洞宗の 寺院です。 山門は、寛政9年(1797)に建立された 竜宮造りの珍しい唐風山門です。 入母屋銅板葺 、二重軒、扇垂木造の建築物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 大山祇神社の石段 福島県大沼郡昭和村喰丸 |
大山祇神社の石燈篭 福島県大沼郡昭和村喰丸 |
大山祇神社の石鳥居 福島県大沼郡昭和村喰丸 |
| 石段は63段中61段目を除いてすべて一枚板で作 られています。 |
石燈籠2基は同型ですが、左は天保4年(1833)に 寄進され、右は明治27年(1894)に造立されました |
石鳥居は神明居型で延享4年(1747)に造立されま した。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 八幡神社の石鳥居 福島県大沼郡昭和村両原 |
小野観音堂 福島県南会津郡下郷町湯野上堂後甲386 |
旧山王茶屋 福島県南会津郡南会津町 糸沢字西沢山3692-20 奥会津博物館 |
| 宝永2年(1705)に造立されました。 高さ3.17m 、柱間2.3m、柱径26cmで、細身のためコンクリ ートで基壇を支えています。 イチョウ-昭和村天然記念物 |
小野観音堂は文化10年(1813)に建立され、御蔵入 三十三観音霊場の第十番札所に選定されました。 本堂宇は、唐禅宗様丸柱三間寄棟造、擬宝珠高欄 回縁がめぐり、正面蔀戸に花頭窓、重厚な二重繁垂 木の建物です。 |
山王茶屋は南山通り(下野街道)の山王峠入口に 建っており、宿駅間休憩所として利用されていまし た。 明治2年(1869)に再建された、茅葺、12間 ×5間の建物で、茶屋とはいえ本陣形式の格も備 えられていました。 旧猪股家住宅-福島県指定重要文化財 |
 |
||
 |
 |
|
| 旧斎藤家住宅 福島県南会津郡南会津町界字川久保552 奥会津南郷民族館 |
セイロウ作り板倉 福島県南会津郡桧枝岐村 |
|
| 天明年代(1780年代)に建築された、寄棟造、茅葺 、平屋建て、馬屋中門造りの曲がり家です。 間口 七間半、奥行き四間の主棟の下手土間前方に、間 口三間、出三.七五間の曲りを突き出した形です。 旧山内家住宅-福島県指定重要文化財 |
板倉は家事から大切な穀物を守るために、家から離 れた畑の中に建てられた穀物庫です。 最も古い形 の板倉で、柱を使わず厚さ10cmほどの板をセイロウ のように組み合わせたもので、釘等の金具は一切使 われていません。 屋根は下葺の板の上に樺の皮を 敷き、その上に楢の割板を葺いています。 奈良の正 倉院と同じ建築様式の建物です。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 善導寺 本堂 福島県郡山市清水台1-1-23 |
善導寺 庫裏 福島県郡山市清水台1-1-23 |
善導寺 鐘楼 福島県郡山市清水台1-1-23 |
| 明治42年(1909)に建築された木造平屋建、入母 屋造、桟瓦葺、正面向拝付の建築面積322㎡本 堂建築の建物です。 |
明治16年(1883)に建築された木造平屋一部2階 建、鉄板葺、建築面積282㎡の建物です。 本堂 北側に廊下で連結して建ち、入母屋造の東妻面を 正面としています。 東西に細長い建物で、屋根の 南面には明かり窓を設けています。 |
昭和33年(1958)に建築された木造、瓦葺、面積 14㎡の建物です。 桁行三間梁間一間、切妻造 本瓦葺で、高欄付の縁を廻らせて二階建風とし、 法隆寺鐘楼に類似した形態をもっています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 如寶寺 書院 福島県郡山市堂前町4-24 |
安積疏水麓山の飛瀑 福島県郡山市麓山1-347 |
郡山市公会堂 福島県郡山市麓山1-8-4 |
| 天保15年(1844)に建築され、明治28年(1895) に移築された木造2階建、瓦葺、建築面積173㎡ の建物です。 白河市に建っていた迎賓施設を移 築したと伝えられています。 |
明治15年(1882)に建造された、石造、堤長14m 、堤高8m、水路延長23m付の石造構造物です。 猪苗代湖から引かれた安積疏水の最終地点、麓 山公園の一角に築かれています。 約1.8mの越 流部を突起付石積柱で挟み、その両脇に土留壁、 底部に水叩き及び水路を築いています。 |
大正13年(1924)に建築された、鉄筋コンクリート 造2階建、銅板葺、建築面積1102㎡、塔屋付の 建物です。 郡山市制施行を記念して市中心部に 建てられました。 連続半円アーチの柱廊と、窓台 受、上げ下げ連窓、縦長ガラス面で垂直性を強調 した塔屋を設けています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 日本基督教団若松栄町教会 福島県会津若松市西栄町8-37 |
向瀧玄関 福島県会津若松市東山町湯本字川向200 |
向瀧客室棟(花月の間、梅の間他) 福島県会津若松市東山町湯本字川向200 |
| 明治44年(1911)に建築された木造二階建、塔屋部 三階、鉄板葺、建築面積208㎡の建物です。 木造 下見板張りのゴシック式教会堂で会堂部の外郭はラ テン十字を描いています。 |
向瀧は江戸時代に「きつね湯」の愛称で親しまれた会津藩の指定保養所で、明治6年(1873)に民間に払い下 げられ旅館となりました。 |
|
| 玄関は、浴場「きつね湯」がある建物です。 大正2 年(1913)頃に建てられた、木造2階建、入母屋造、 瓦葺、建築面積636㎡建物です。 |
向瀧客室棟(花月の間,梅の間他)は明治30年代( 1897-1906)に建てられた、木造2階建、瓦葺、建築 面積248㎡の建物です。 |
|
 |
||
 |
 |
|
| 興國山徳昌寺 本堂 福島県南会津郡南会津町 田島字寺前甲2970 |
興國山徳昌寺 庫裡 福島県南会津郡南会津町 田島字寺前甲2970 |
|
| 徳昌寺は曹洞宗の寺院です。 本堂は天保15年 (1844)に建てられた木造平屋建、銅板葺、建築面 積327㎡の建物です。 |
徳昌寺は曹洞宗の寺院です。 庫裡は文政3年(1 820)に建てられた木造平屋建、銅板葺、建築面積 297㎡の建物です。 南面が入母屋造、北面が切 妻造になります。 |
|