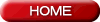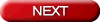茨城県 茨城県 |
 |
|
 |
||
 |
 |
|
| 佐竹寺 本堂 茨城県常陸太田市天神林2404 |
笠間稲荷神社 本殿 茨城県笠間市笠間39 |
|
| 佐竹寺は真言宗豊山派のお寺です。 大同2年(807)又は寛和元年(985)創建の寺院で、 源昌義(佐竹氏)の祈願所でした。 天文12年(154 3)に焼失し、天文15年(1546)に佐竹城(太田城) の鬼門除けとして現在地に再建、その際佐竹城に 正対するよう北東向きに建てられました。 本堂は、桁行五間、梁間五間、寄棟造、茅葺の建 物で、周囲にこけら葺の裳階を巡らし、正面中央に 唐破風を付けています。 坂東三十三観音札所第22番 |
笠間稲荷神社は、白雉2年(661)に創建された神社 で、日本三大稲荷のひとつとされています。 本殿は、 万延元年(1860)の再建で、外陣(本殿)、 内陣(旧拝殿)からなる複合社殿です。 銅瓦葺総欅 の権現造で、周囲には後藤縫之助の作「三頭八方 睨みの龍」、「牡丹唐獅子」、弥勒寺音八と諸貫万五 郎の作「蘭亭曲水の図」等の精巧を極めた彫刻が施 されています。 八重のフジ-茨城県指定天然記念物 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 西蓮寺 仁王門 茨城県行方市西蓮寺504 |
西蓮寺 相輪とう 茨城県行方市西蓮寺504 |
善光寺楼門 茨城県石岡市太田940-1 |
| 西蓮寺は延暦元年(783)に開山した天台宗のお寺で、常陸の高野山ともいわれています。 明治16年(188 3)の火災により本堂、薬師堂などを焼失したが、山門と相輪とうは焼失を免れました。 大イチョウ(1号、2号)-茨城県指定天然記念物 |
善光寺は真言宗豊山派のお寺です。 文亀元年(1501)、小田城主小田成治は母堂の願い からこの地に善光寺を選び建立しました。 元禄14年(1701)に現在地に移されましたが、当時 の建築物は楼門だけとなってしまいました。 楼門の確かな建立時期は不明ですが、室町時代中 期の特色を示しています。 現在の楼門は平屋建で ですが、屋根裏を見ると当初は楼門(二階建)として 建立されたことがわかります。 三間一戸、寄棟造、茅葺 |
|
| 仁王門は、天文12年(1543)に建立されたもので、 もとは三間一戸の楼門(二階建)でした。 天正4年 (1576)の修理後、寛政年間(1785~1801)に楼門 の二階部分を取り壊して山門(一階建)となりました 。 その後、安政7年(1860)に現在の地に移築され 、仁王門に改められたものです。 三間一戸楼門、 寄棟造、とち葺形銅板葺の建物です。 |
相輪とうは天台宗の象徴とされるもので、比叡山延 暦寺、日光輪王寺のものとならび、日本三相輪とう のひとつになります。 元冦(弘安の役)の戦勝を記念して、弘安10年(12 87)に建立したものです。 高さ9.16mで、基壇、 とう身、頭部の三つに分けられ、全体として錫杖形 をしています。 |
|
 |
||
| 鹿島神宮 茨城県鹿嶋市宮中2306-1 創建は神武天皇1年(紀元前660)と伝えられていま す。 「常陸国風土記」では、神代の時代に神八井 耳命の血を引く肥国造の一族だった多氏が上総国 に上陸、開拓を行いながら常陸国に勢力を伸ばし、 氏神として建立されたのが現在の鹿島神宮の起源 だとされています。 平安時代に、「神宮」の称号で呼ばれていたのは、 延喜式神名帳によると伊勢神宮、鹿島神宮、香取 神宮の3社だけでした。 楼門回廊-鹿嶋市指定有形文化財 鹿島神宮樹叢-茨城県指定天然記念物 |
 |
 |
| 鹿島神宮 拝殿 | 鹿島神宮 本殿 | |
| 現社殿は、本殿、拝殿、石間、幣殿の4つの棟よりできています。 現在の社殿は、江戸幕府の二代目将軍の徳 川秀忠公が、元和5年(1620)に奉納したものです。 本殿、石間は漆塗りで柱頭や組物などには華麗な極彩色が施されていますが、幣殿、拝殿は白木のままで す。 |
||
| 拝殿は桁行五間、梁間三間の一重、入母屋造、向 拝一間、檜皮葺の建物です。 |
本殿は三間社流造、向拝一間、檜皮葺の建物で す。 |
|
 |
 |
 |
| 鹿島神宮 楼門 | 鹿島神宮 仮殿 | 鹿島神宮 摂社奧宮本殿 |
| 寛永11年(1634)に水戸光圀公の父、水戸初代藩 主の徳川頼房公が奉納したものです。 間口を三間とし中央一間を出入口とする三間一戸 、二階建ての八脚門です。 屋根は入母屋造り、銅 板葺きですが、元は檜皮葺きでした。 総朱漆塗り とし、わずかに欄間などに彩色を飾る控え目な意匠 で統一されています。 |
仮殿は元和5年(1619)、現本殿の造替時に建立さ れたものです。 桁行三間、梁間二間、向拝一間、入母屋造りの建 物です。 仮殿は本殿の造営に際して神霊を仮安置 するために設けられた建物で、権殿ともいいます。 正面には三間とも板扉を構えるなど本格的な建築 ですが、内部は一室として祭壇などは設けておらず 、装飾も一部にのみ漆彩色を施し、ほかは白木の 松とい質素なものです。 |
この建物は慶長10年(1605)、徳川家康公によって 造営された神宮の旧本殿で、元和5年(1619)、徳 川秀忠公の社殿造替に際して現在地に移され、奧 宮本殿となりました。 三間社流れ造りの建物で、前庇の前に一間の向拝 を付しています。 身舎の梁間を二間とし、縁を四方 に巡らし、扉口も正面中央間に設けるのみで、ほか は連子窓や板壁とするなど、神社本殿の古い形式 を伝えています。 白木造りの簡潔な建物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 大塚家住宅 茨城県つくば市栗原835 |
大宝神社 本殿 茨城県下妻市大宝667 |
坂野家住宅 表門 茨城県常総市大生郷町2037 水海道風土博物館 |
| 大塚家は、太田道灌の子孫で、小田家の家臣でし たが、後に帰農し、代々の名主を務めた旧家です。 現在の建物は正徳から亨保にかけて(18世紀前 期)の建築です。 江戸時代前期の古い農家形式 から、江戸時代後期の新しい民家形式への移行段 階の貴重な建物です。 桁行9.5間、梁行6間、萱葺、寄棟造の建物です。 |
大宝神社は大宝元年(701)に藤原時忠が創建した といわれる神社です。 本殿は天正3年(1575)に焼失してしまったため天 正5年(1577)に下妻城主多賀谷下総守尊経によっ て建立された三間社流造の建物です。 |
坂野家は、この地に土着してから500年になると言 われ、江戸時代には惣名主的存在でした。 その屋 敷地は1haに及ぶ広大な台地全面に位置していまし た。 表門は江戸後期の建立で、切妻造、茅葺の薬医門 です。 |
 |
||
 |
||
| 龍禅寺 三仏堂 茨城県取手市米ノ井467 |
||
| 龍禅寺は平安時代の延長2年(924)の創建また は、承平7年(937)に平将門が創建したとも言わ れる天台宗のお寺です。 三仏堂は永禄12年(1569)に建立された桁行三 間、梁間四間、一重、両側面及び背面もこし付、 寄棟造、茅葺、もこし板葺の建物です。 三仏堂 の名前の由来となった釈迦如来、阿弥陀如来、弥 勒菩薩の三尊を祀っています。 古木-イヌマキ・モチノキ・キンモクセイ |
||
 |
||
 |
||
| 笠間城櫓 茨城県笠間市笠間323 真浄寺 |
||
| 笠間城は、鎌倉時代の承久年間(1219-1221)に下 野守護宇都宮頼綱の甥、笠間時朝によって築城さ れたと言われています。 笠間城には、天守櫓の他 に八幡台と宍ヶ崎に物見櫓があり、この櫓は八幡 台にあった櫓で、明治13年(1880)に移築、復元さ れました。 木造二層の入母家造で瓦葺き、窓は 一階の左右に3つあり、二階は四方に窓が3つず つあります。 周りは塗籠といわれる白壁で、柱、 貫、庇まで木地の見えないように全表面を塗ってあ ります。 平時は武器貯蔵庫、戦時は物見に使わ れました。 |
||
 |
||
 |
 |
 |
| 厳島神社 本殿 茨城県鉾田市子生877 |
万福寺 阿弥陀堂 茨城県行方市羽生745 |
万福寺 仁王門 茨城県行方市羽生745 |
| 厳島神社は、承暦2年(1078)安芸宮島の厳島神社 から分社されたと伝えられています。 現在の社殿 は元禄10年(1697)年に建てられたもので、向拝社 の竜の彫刻が,一木造になっている点に特色があ ります。 拝殿-鉾田市有形文化財 |
万福寺の天台宗のお寺です。 創建は平重盛の家臣平貞能が重盛を祀り菩提を弔うために建立したのが 始まりと伝えられています。 当初は芹沢にありましたが元禄年間(1688~1704)に藩主徳川光圀の命に より現在地に移されました。 |
|
| 阿弥陀堂は三間四方、寄棟、茅葺の建物で、四手 先萱葺の念仏三味を修める常行堂様式に造られて います。 |
仁王門は天正6年(1578)に逢善寺に建てられたも のを享保9年(1724)に移築したものです。 三間一 戸、八脚、単層、入母屋、茅葺の建物で、全体を朱 色に塗られています。 |
|
 |
||
| 長勝寺 茨城県潮来市潮来428 長勝寺は、文治元年(1185)に源頼朝が開基した臨済宗妙心寺派のお寺です。 元禄年間(1688-1704)には徳川光圀により堂宇が再建されました。 |
||
 |
 |
 |
| 長勝寺 本堂 | 長勝寺 楼門 | 長勝寺 方丈・書院・玄関・庫裡・穏寮 |
| 本堂は方七間、一重入母屋造、茅葺の仏殿で、棟 上に源氏の定紋「笹りんどう」が配され、周囲は板 葺もこしがあります。 建立年代は詳かではありませんが、軒周りその他 細部に桃山時代の様式手法がうかがわれます。 |
三間一戸、二重二階門、入母家造茅葺(現柿葺型銅 板葺)の山門です。 一重屋根は棧瓦葺、軒は二重 の垂で雄大な唐様様式の建物です。 建立年代は、細部の様式手法により桃山時代の建 立と思われます。 |
木造平屋建ての約500㎡の建物です。 東に隠寮、 西に方丈、南に庫裡、北に書院を配した寺院形式の 建物です。 現在は棧瓦葺ですが、以前は茅葺でし た。 建立年代は、細部の様式手法により元禄時代 中期の建立と思われます。 |
 |
||
| 雨引観音(楽法寺) 茨城県桜川市西本木1 坂東三十三観音札所第24番 楽法寺は真言宗豊山派の寺院です。 寺伝によれば、用明天皇2年(587)中国(梁)出身の法輪独守居士によって創建されたといわれています。 第三十三代推古天皇は勅願のみ寺と定め、 天平年中(730)には第四十五代聖武天皇、光明皇后から 安 産祈願の根本道場と定めて勅願寺となされました。 また、弘仁12年 (821)夏、大かんばつが国中を見舞うや、嵯峨天皇は写経し降雨を祈ったところ、大雨に 潤ったため勅命 によって山号を雨引山と定められたものです。 現在は「安産子育祈願」の寺として信仰されています。 黒門、鬼子母神堂-桜川市指定文化財 宿椎-桜川市指定天然記念物 |
 |
|
| 雨引観音 仁王門 | ||
| 現在の建物は、天和2年(1682)に再建されたもの です。 二階作りで楼門形式をとり、下層正面の左 右には仁王像を安置しています。 柱はすべて丸柱 で、中央出入り口の鏡天井には竜と天女の絵が画 かれ、繻欄彩色を施すなど彩色にも華やかさがみら れます。 |
||
 |
 |
 |
| 雨引観音 本堂 | 雨引観音 多宝塔 | 雨引観音 東照山王社殿 |
| 現在の建物は、天和2年(1628)に建立されたもの です。 桁行、梁間ともに五間の正方形の平面をも ち、全面の梁間二間を外陣、奥の三軒を内陣とする 密教本堂特有の形態をとっています。 |
建長6年(1254)に建立された三重塔が大破してしま いました。 現在の建物は、嘉永6年(1853)に多宝 塔として再建されたものです。 高さ22m、銅板瓦 葺きの屋根をもちます。 |
現在の建物は、享保12年(1727)に再建されたもの です。 東照大権現(徳川家康)とともに、地主大権 現(徳川家光)が合祀されています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 月山寺 書院 茨城県桜川市西小塙1677 |
薬王院 三重塔 茨城県桜川市真壁町椎尾3178 |
羽黒神社 本殿 茨城県筑西市甲37 |
| 月山寺は延暦15年(796)に法相宗の寺として徳一 が開基し、永享2年(1430)に光栄が再興して天台 宗の寺となり、元和元年(1615)に現在地へ移され ました。 書院は、寛永年間(1661~73)に焼失し た後に談議所として再建されたもので、建築手法に 江戸時代初期のものが見られます。 桁行17.3m 、梁間11.5mの簡素な住宅風の建築物です。 本堂、境内山王社本殿、中門-桜川市指定文化財 |
薬王院は標高200mの椎尾山中にあり、延暦元年 (782)最仙上人による開山と伝えられる天台宗の古 刹です。 椎尾薬師の名前で知られています。 現在の塔は、天文19年(1550)の大火で焼失したも のを宝永元年寛文6年(1666)から宝永元年(1704) の約40年の歳月をかけて再建したものです。 高さ25m、銅板葺きの屋根をもちます。 本堂、仁王門-桜川市指定文化財 スダジイ樹叢-茨城県指定天然記念物 |
羽黒神社は、文明13年(1481)下館城主の水谷 家初代勝氏が勧請したものです。 本殿は、寛永11年(1634)に建立し、享保15年( 1730)に銅板葺に修復された欅一部檜材彩色、間 口8尺の一間社流造の建物です。 旧拝殿-筑西市指定文化財 |
 |
||
| 筑波山神社 茨城県つくば市筑波1 筑波山神社は筑波山を境内とした、古代山岳信仰 に始る国内屈指の古社です。 西峯男体山頂(871m)の磐座に筑波男大神(伊弉 諾尊)を、東峯女体山頂(877m)の磐座に筑波女大 神(伊弉冊尊)を祀っています。 山下の南面中腹(270m)に拝殿があり、これより山 上の境内地「筑波山」を御神体として拝する古代の 形が維持されています。 平安時代に奈良から僧徳一が来住し、この地に中 禅寺を開創しました。 江戸時代になって、中禅寺 は江戸城の鬼門を守る祈願所として定められ、寛 永10年(1633)には全山の堂舎が将軍家により再 建されました。 境内地は、筑波山南面を主に370haに及びます。 随身門-市指定文化財 まるばくす-市指定天然記念物 |
 |
 |
| 神橋 | 筑波山神社境内社 厳島神社本殿 | |
| 寛永10年(1633)に三代将軍徳川家光が寄進し、元 禄15年(1703)に五代将軍綱吉が改修したもの。 両妻の太瓶束の左右に妻面を覆いつくすようにのび る唐草の笈形や、虹梁上の板蟇股に、安土桃山時 代の豪壮な遺風が見られます。 桁行4間、梁間1間の切妻造、柿葺で妻入りの反橋 です。 |
寛永10年(1633)に三代将軍徳川家光が寄進した ものです。 本殿は方一間、妻入正面に向拝を設けた春日造で す向拝蟇股に蛇の彫物があります。 向拝と身舎は 水平な虹梁でつなぎ、その中央に優美な蟇股を置 いています。 垂木は大面取の吹寄せ垂木としてい る点が春日、日枝神社と異なります。 |
|
 |
 |
 |
| 春日神社、日枝神社両社拝殿 | 筑波山神社境内社 春日神社本殿 | 筑波山神社境内社 日枝神社本殿 |
| 寛永10年(1633)に三代将軍徳川家光が寄進したも のです。 春日神社、日枝神社両社拝殿は両本殿の中央前面 に建っています。 桁行6間、梁間2間、入母屋造で 正、背面中央に軒唐破風をつけています。 柱間は 外まわりを半蔀とし、内部は中央両側に二本溝の敷 居と鴨居がある割拝殿形式です。 |
寛永10年(1633)に三代将軍徳川家光が寄進したものです。 春日神社の屋根裏から寛永10年の墨書が 発見され、建立年次も確定されました。 春日神社及び日枝神社は桁行2間、梁間2間の同形同大の三間社流造です。 向拝中央の蟇股は春日神社が鹿、日枝神社が猿の彫物で、その他彩色模様や木鼻の絵様繰形に若干の 差違はありますが、構造形式は全く同一です。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 鹿島神社 本殿 茨城県つくば市大形1264 |
吉沼八幡神社 本殿 茨城県つくば市吉沼1456 |
吉沼八幡神社 本殿覆屋 茨城県つくば市吉沼1456 |
| 鹿島神社は、日本武尊東征の際立ち寄った時に神 宝をもらい受けて祭ったのが始まりと伝えられてい ます。 本殿は、棟札によれば、元文2年(1737)斧 始、延享2年(1745)成就とあります。 一間社流造 、木羽葺で、正面及び両側面に扉がある珍しい建 物です。 全体が華麗な彫刻で飾られ、特に廻縁下 は瑞雲の彫刻で覆われています。 |
寛治元年(1087)、源義家が後三年合戦の折この地を訪れ戦勝祈願したのが始まりと言われています。 | |
| 本殿は貞享2年(1685)に再建されたものです。 一間社流造、茅葺の建物で、建物全体が朱色に着 色され細部には豊かで精巧な彫刻が施され極彩色 で彩られています。 |
覆屋は慶応3年(1867)に建立されました。 四間四 面、入母屋造、桟瓦葺の建物でで、土台を回して方 柱を立て頭貫、台輪を組み、獅子の掛鼻を付けてい ます。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 一ノ矢八坂神社 本殿 茨城県つくば市玉取2617 |
金村別雷神社 本殿 茨城県つくば市上郷8319-1 |
金村別雷神社 本殿覆屋 茨城県つくば市上郷8319-1 |
| 八坂神社の創立は平安時代初期貞観年中といわれ ています。 神社には延宝4年(1676)、宝永8年(17 11)の2枚の棟札があります。 本殿は、一間社流造りで前に拝殿と幣殿を設けてい ます。 向拝は角柱で、身舎とは海老虹梁形の彫刻 で連結し高い浜床を設け、屋根はこけら葺きです。 縁下の部分と縁上の部分とが別個につくられている 珍しい形式です。 彫刻を多用し、柱や壁面に地文 彫りを施している装飾豊かな建物です。 拝殿、覆屋-市指定文化財 |
金村別雷神社は承平元年(931)の創建です。 関東三雷神の一つに数えられなど信仰を広めました。 拝殿、神楽殿、回廊-つくば市指定有形文化財 |
|
| 本殿は宝永5年(1708)の建立で、一間社流造、こけ ら葺の建物で、全体が精巧な彫刻で施され、屋根妻 面には力士像が彫り込まれています。 |
覆屋は、天保2年(1831)に改修された四間四面、入 母屋の建物です。 |
|
 |
||
| 不動院(板橋不動尊) 茨城県つくばみらい市板橋2370 清安山願成寺不動院は、関東三大不動尊のひとつで、地元では「板橋のお不動さん」と呼ばれている真言宗豊山派のお寺です。 不動院縁起によると、大同3年(808)弘法大師が諸国行脚の折、自ら彫刻したのが御本尊の不動明王です。 以来、七堂迦藍が整いました。 その後、幾度か兵 火にかかり、文禄年間に本堂が、元禄年間に楼門が建立され、更に安永9年(1780)に三重塔が竣工されました。 社の創建は明らかではありませんが、社記によると大同2年(807)に紀州熊野より勧請され、熊野郷の鎮守として成立しましたが、さらに後白河天皇の勅によって 、熊野神社の規矩をとって社殿を建立したものと伝えられています。 |
||
 |
 |
 |
| 不動院 楼門 | 不動院 本堂 | 不動院 三重塔 |
| 元禄年間(1688-1703)の建立で、朱塗り、入母屋 造二重垂木で左右に力強い阿、叫の二王像が安 置されています。 屋根も瓦棒銅板葺としています が、もとは瓦葺でした。 桁行3間、梁間2間。 初層各無柱間の頭貫上には 花鳥の彫物をもつ蟇股を配し、頭貫の木鼻は牡丹 及び菊花を篭彫としています。 |
文禄年間(1592-1595)建立の二重屋根、入母屋造 の建物です。 重層形式は,密教寺院として例は少なく、地方建造 物としては豪壮華麗な建物です。 五間四方、重層、総欅造で、,内外を丹塗りとし、要 所に極彩色を施しています。 形は正方形で内、脇、 外陣を区分し、天井は化粧屋根裏としています。 |
安永元年(1772)に建立された高さ25mの塔です。 廻縁付銅板葺で中央の間を扉としています。 随所 に彫刻を施し、尾垂木は龍頭彫刻とするなど、茨城 県内の近世建築に特徴的な装飾の多い手法を示し ています。 初重脇間腰長押上を連子窓とせず、大きく文字を配 しているのは、他に例のない珍しいものです。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 高徳寺 山門 茨城県久慈郡大子町上郷2056 |
天神社 本殿 茨城県笠間市大渕175-1 |
城山稲荷神社 本殿 茨城県笠間市笠間6-1 |
| 高徳寺は永正元年(1504)に創建された曹洞宗のお 寺です。 山門は間口3.46m、奥行3.52m、木造 茅葺きで、柱は4本のけやき丸柱で組み立てられた 室町末期の建物です。 カシ・カヤ抱き合い木-古木 |
天神社は、鎌倉時代の承久年間(1219-1221)に初 代笠間城主藤原時朝が城の鬼門にあたる大淵に領 国鎮護の神として天神社を祀ったと言われています 本殿は明治24年(1891)の建立で、神明造、総欅造 、銅板葺の建物で、多数の装飾彫刻で飾られていま す。 ツクバネガシ-市天然記念物 |
城山稲荷神社は、城山新左衛門稲荷とも云われ、 胡桃下紋三郎稲荷(笠間稲荷)、士当原与兵衛稲 荷と共に、笠間三稲荷の一つに数えられています。 本殿は江戸時代中期の建立で、間口0.86m、奥 行1.5m、軒張2.0m×2.6mに、間口1.4m、 高さ3.1mの向拝が付いている柿葺の建物です。 各所に彫刻が施され、社殿全体に彩色に塗られ、 側面には右三巴の神紋があり、金箔が施されてい ます。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 笠間城門 茨城県笠間市笠間824 |
笠間城門 茨城県笠間市笠間818 |
厳島神社 拝殿 茨城県鉾田市子生877 |
| 笠間城の門を明治時代初期に移築したものです。 間口3.95m、奥行1.8m、高さ4.5m、軒張1.2m の四脚門で切妻造、瓦葺きで薬医門です。 |
笠間城の門を明治時代初期に移築したものです。 間口3.95m、奥行1.8m、高さ4.5m、軒張1.2m の四脚門で切妻造、瓦葺きで薬医門です。 |
厳島神社は、承暦2年(1078)安芸宮島の厳島神社 から分社されたと伝えられています。 本殿-茨城県有形文化財 |
 |
||
 |
 |
 |
| 鹿島神宮 楼門回廊 茨城県鹿嶋市宮中2306-1 |
雨引観音(楽法寺) 茨城県桜川市西本木1 坂東三十三観音札所第24番 仁王門、本堂、多宝塔、東照山王社殿-県指定有形文化財 宿椎-市指定天然記念物 |
|
| 寛永11年(1634)に水戸光圀公の父、水戸初代藩 主の徳川頼房公が奉納したものです。 本殿、拝殿、楼門、仮殿、摂社奧宮本殿 -国指定重要文化財 鹿島神宮樹叢-茨城県指定天然記念物 |
雨引観音 黒門(薬医門) | 雨引観音 鬼子母神堂 |
| 慶長4年(1599)の建立です。 元は楽法寺の表門で、麓の集落中央に位置してい たものを移築したものです。 |
宝永期(1704~11)の建立です。 一間社流造の建物で、足利尊氏を祀った堂です。 屋根には足利氏の定紋が付いています。 |
|
 |
||
| 月山寺 茨城県桜川市西小塙1677 書院-茨城県指定有形文化財 |
||
 |
 |
 |
| 月山寺 本堂 | 月山寺 境内山王社本殿 | 月山寺 中門 |
| 延宝8年(1680)の建立です。 桁行十一間、梁間六間 |
正徳5年(1715)の建立です。 一間社流造、切妻造 |
宝暦4年(1754)の建立です。 長屋門 |
 |
||
 |
 |
 |
| 薬王院 茨城県桜川市真壁町椎尾3178 三重塔-茨城県指定有形文化財 スダジイ樹叢-茨城県指定天然記念物 |
薬師堂 本堂 茨城県筑西市甲897 |
|
| 薬王院 本堂(薬師堂) | 薬王院 仁王門 | 現在の堂宇は元禄4年(1691)の再建と伝えられ ています。 木造欅材入母屋造、平屋銅板葺の三 間四面、四囲を朱色で塗られた建物です。 |
| 延宝8年(1680)の建立です。 | 貞亨2年(1685)の建立です。 | |
 |
||
 |
 |
 |
| 羽黒神社 旧拝殿 茨城県筑西市甲37 |
大聖寺 茨城県土浦市永国203 大聖寺は、長徳元年(995)に創建された真言宗豊山派のお寺です。 檀林所格の本寺として隆盛し末寺16 0余ヵ寺を抱える大寺として栄えました。 |
|
| 羽黒神社旧拝殿は寛永11年(1634)に本殿とと もに造営されました。 桁行三間、梁間二間正面 に一間の向拝を設けています。 現在は瓦棒銅板 葺の寄棟造ですがもとは茅葺でした。 本殿-茨城県指定文化財 |
大聖寺 山門 | 大聖寺 四脚門 |
| 貞享2年(1685)に土浦城主、松平信興から寄進さ れました。 桁行5.6m、梁間3.6m、切妻、茅葺 の薬医門です。 |
貞享年間(1684-1687)の建立です。 桁行3.4m、梁間3.93m、切妻、茅葺の四脚門で す。 |
|
 |
||
 |
 |
|
| 鹿島神社 茨城県土浦市中村西根817-1 応永2年(1395)、稲敷郡阿見町竹来の阿弥神社の祭神を勧請して創建された神社です。 |
||
| 鹿島神社 拝殿 | 鹿島神社 鳥居 | |
| 江戸時代後期の建立です。 桁行三間、梁間三間、 茅葺、寄棟造の建物です。 桁行中央の一間は、実 寸で二間分あります。 |
柱の前後に袖柱をもった両部鳥居で、建築年代は 不明です。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 筑波山神社 随身門 茨城県つくば市筑波1 |
一ノ矢八坂神社 茨城県つくば市玉取2617 本殿-茨城県指定文化財 |
|
| 随身門は、寛永10年(1633)に三代将軍家光によっ て寄進されましたが、宝暦4年(1757)に焼失。 現在の門は文化8年(1811)に再建されたものです。 桁行5間2尺、梁間3間の八脚楼門です。 神橋、春日神社本殿、日枝神社本殿、両社拝殿 厳島神社本殿-茨城県指定文化財 まるばくす-市指定天然記念物 |
一ノ矢八坂神社 拝殿 | 一ノ矢八坂神社 覆屋 |
| 宝永8年(1711)の建立です。 | 江戸後期の建立です。 | |
 |
||
 |
 |
 |
| 金村別雷神社 拝殿 茨城県つくば市上郷8319-1 |
金村別雷神社 神楽殿 茨城県つくば市上郷8319-1 |
金村別雷神社 回廊 茨城県つくば市上郷8319-1 |
| 金村別雷神社は承平元年(931)の創建です。 関東三雷神の一つに数えられなど信仰を広めました。 本殿、本殿覆屋-茨城県指定有形文化財 | ||
| 拝殿は明治12年(1879)の再建です。 入母屋造、 瓦葺、千鳥破風、向拝付の建物です。 |
神楽殿は明治12年(1879)の再建です。 入母屋造 、瓦葺、高欄付の建物です。 |
回廊は明治12年(1879)の再建です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 随翁院 本堂 茨城県つくば市上郷3148 |
金村別雷神社 神楽殿 茨城県つくば市上郷8319-1 |
金村別雷神社 回廊 茨城県つくば市上郷8319-1 |
| 随翁院は曹洞宗の寺院です。 寛正5年(1465)に創建され、永正10年(1513)に現在地に移転しました。 | ||
| 本堂は寛政10年(1798)の建立です。 | 山門は文政9年の建立です。 | 鐘楼は明治31年(1898)の建立です。 |
 |
||
 |
 |
|
| 一言主神社 本殿 茨城県常総市大塚戸町875 |
日枝神社 本殿 茨城県常総市菅生町4892 |
|
| 一言主神社は、大同4年(809)年に大和国葛上郡葛 城の一言主神を迎え鎮斎したと伝えられています。 本殿は元禄13年(1700)に再建された桁行2.7m、 梁間2.3m、一間社流造、檜皮葺風銅板葺の建物 です。 |
日枝神社は、承平元年(931)の創建と伝えられてい ます。 本殿は明治5年(1872)に再建された桁行2 .65m、梁間2.25m、一間社流造、瓦葺の建物で す。 名工、後藤縫之助の手による豊富な彫刻群が 特色です。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 荒川家住宅 主屋 茨城県筑西市甲868 |
荒川家住宅 店蔵 茨城県筑西市甲868 |
荒川家住宅 旧店蔵 茨城県筑西市甲929-1 |
| 荒川家住宅は酒店を営んでいますがかつては醤 油の醸造業を営んでいました。 昭和8年(1933) に建造された木造3階建、瓦葺、建築面積139㎡ の建物です。 モルタル塗のアール・デコ調の洋 館で、3階の屋根は宝形屋根とし帝冠様式的雰囲 気を感じさせる特異な外観意匠をもっています。 |
店蔵は明治40年(1907)に建造された土蔵造2階 建、瓦葺、建築面積99㎡の建物です。 主屋の東 に隣接する建物で、間口五間半、奥行三間で正面 に一間分の下屋を差し出しています。 |
旧店蔵は明治41年(1908)ころに建造された土蔵 造、切妻造2階建、瓦葺、桁行9.5m、梁間6.8 m、建築面積68㎡の建物です。 袖蔵として3階 建ての洋館を増築しました。 |
 |
||
 |
||
| 一木歯科医院 茨城県筑西市甲12 |
||
| 大正11年(1922)に建造された木造2階建、鉄板 葺、建築面積30㎡の建物です。外見は洋風です が柱や梁は木造で、診療室を除く患者待合室及び 2階の二間が和室です。 木造鐵網コンクリート仕 上げの数少ない遺存例として貴重です。 |
||