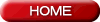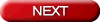栃木県 栃木県 |
 |
|
 |
||
 |
鑁阿寺 本堂(大御堂) 国指定史跡 | 栃木県足利市家富町2220 |
| 鑁阿寺は真言宗大日派の本山です。 源姓足利氏二代目の足利義兼(足利尊氏の7代前)が建久7年(1 196)に自宅である居館に持仏堂を建て、守り本尊として大日如来を祭ったのが始まりといわれています。 その後、三代目の足利義氏が堂塔伽藍を建立し足利一門の氏寺としました。 周囲に土塁と堀をめぐらした 寺域はほ正方形で、約4万㎡あり、鎌倉時代の武家屋敷の面影を今に伝えています。 本堂は正安元年(1299)に再建された建物です。 桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、正面向拝三間 、軒唐破風付、背面向拝一間、本瓦葺の建物です。 鎌倉時代初期の禅宗様で唐様と和様の折衷とする など鎌倉時代の代表的な寺院建築です。 平成25年8月7日、国重要文化財から国宝に指定されました。 鐘楼、経堂-国重要文化財 楼門・東門・西門・多宝塔・御霊屋・太鼓橋-県指定有形文化財 中御堂(不動堂)・智願寺殿御霊屋(蛭子堂)・宝庫・北門・水屋-市指定有形文化財 イチョウ-県指定天然記念物 |
||
 |
||
 |
 |
 |
| 旧青木家那須別邸 栃木県那須塩原市青木27 |
木幡神社 楼門 栃木県矢板市木幡1194-1 |
木幡神社 本殿 栃木県矢板市木幡1194-1 |
| 青木周蔵(1844-1914)は、ドイツ公使や外務大臣 などを歴任した外交官です。 この建物は、那須別 邸として、明治21年(1888)に建築されました。 当時は中央の2階建て部分だけでしたが、増築を重 ね、明治42年(1909)に現在の形になりました。 |
木幡神社の創建は延暦年間(782-806)、坂上田村麻呂が東夷東征の際、戦勝祈願をし見事勝利を得たこと から許波多神社を勧請したことが始まりと言われています。 杉社叢-市天然記念物 |
|
| 楼門は室町時代中期に造営された、三間一戸、入 母屋、銅板葺きの八脚楼門です。 |
本殿は室町時代中期に造営された三間社、流造り、 銅板葺きの建物です。 |
|
 |
||
 |
 |
|
| 荒井家住宅 主屋 栃木県矢板市立足192 |
荒井家住宅 表門(長屋門) 栃木県矢板市立足192 |
|
| 荒井家は旧庄屋を務めた家柄です。 江戸時代初 期の延宝年間(1673~1681)に建てられた古民家 です。 桁行24.2m、梁間10.3m、寄棟造、茅 葺の建物で、間取りは、馬屋、土間、流し、板間、 勝手南間、勝手北間、納戸、中ノ間、座敷、上座敷 になっています。 大カヤ-市指定天然記念物 |
桁行12.9m、梁間4.6m、切妻造、こけら葺の建 物で、主屋と同時期に立てられたものです。 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 二荒山神社 神橋 栃木県日光市上鉢石町 |
古河橋 栃木県日光市足尾町赤倉-本山 |
円通寺 表門 栃木県芳賀郡益子町大沢1770 |
| 二荒山神社は神護景雲元年(767)に創建された 式内社(名神大社)、下野国一宮、旧社格は国幣 中社の神社です。 神橋は日光山内の入口に架か る明治37年(1904)に建造された高欄付の木造反 橋です。 橋長28m、巾7.4m、高さ10.6mあり 、高欄には親柱10本を建て、それぞれに擬宝珠が 飾られ、橋板の裏は黒漆塗で、その他は朱に塗ら れています。 日本三大奇橋(山口県錦帯橋、山梨 県猿橋)の1つに数えられています。 |
古河橋は明治23年(1890)に建造された鋼製単ト ラス桁橋、橋長48.6m、幅員5.2m、橋台2基付 の橋です。 足尾銅山施設の近代化の一環として 渡良瀬川に架設されたドイツ国ハーコート社製の鋼 製のトラス橋です。 足尾銅山において近代最初期 に整備された施設の中で、ほぼ完存する唯一の遺 構です。 |
円通寺は応永9年(1402)に開山された浄土宗の寺 院です。 表門は開山時の応永9年(1402)に建立された切妻 造、茅葺形銅板葺、高さ6.21m、桁行3.11m、 梁間2.80m、平面積8.68㎡の唐様式の四脚門 です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 岡本家住宅 主屋 栃木県宇都宮市下岡本町1624-1 |
岡本家住宅 長屋門 栃木県宇都宮市下岡本町1624-1 |
旧下野煉化製造会社煉瓦窯 栃木県下都賀郡野木町野木3324-1 |
| 岡本家は河内町下岡本の旧家で、庄屋格組頭の家 柄です。 主屋は江戸時代中期に建てられたもので す。 前後2つの部分からなり、前側は桁行7間半、 梁間4間半、後側は桁行10間半、梁間5間半ありま す。 屋根は寄棟造、茅葺です。 |
表門は県下の上層農家に多く見られる長屋門で、桁 行8間、梁間2間の入母屋造、桟瓦葺の建物です。 |
明治23年(1890)に建造された煉瓦及び木造、建 築面積840.0㎡、十六角造、鉄板葺、中央煙突 付、階段二箇所附の建物です。 ドイツのホフマン 式輪窯という煉瓦焼成用の大規模な窯です。 煉 瓦造で平面十六角形の中央に34.3mの煙突を 立て、木造の上屋を架けています。 16の窯があ り、1つの窯で1回に約17,000本の赤煉瓦を生 産することができます。 |
 |
||
| 鑁阿寺 栃木県足利市家富町2220 (国指定史跡) 鑁阿寺は真言宗大日派の本山です。 源姓足利氏 二代目の足利義兼(足利尊氏の7代前)が建久7 年(1196)に自宅である居館に持仏堂を建て、守り 本尊として大日如来を祭ったのが始まりといわれて います。 その後、三代目の足利義氏が堂塔伽藍 を建立し足利一門の氏寺としました。 周囲に土塁 と堀をめぐらした寺域はほ正方形で、約4万㎡あり 、鎌倉時代の武家屋敷の面影を今に伝えています 。 本堂(大御堂)-国宝 楼門・東門・西門・多宝塔・御霊屋・太鼓橋 -県指定有形文化財 中御堂(不動堂)・智願寺殿御霊屋(蛭子堂)・宝 庫・北門・水屋-市指定有形文化財 イチョウ-県指定天然記念物 |
 |
 |
| 鑁阿寺 鐘楼 | 鑁阿寺 経堂 | |
| 鐘楼は建久7年(1192)に足利義兼が建立し、鎌倉 時代後期(1275-1332)に再建された建物です。 桁 行三間、梁間二間、袴腰付、入母屋造、本瓦葺の建 物で、1層目には袴腰が付いており2層目には高欄 が廻され、2重垂木や組物など鎌倉時代建築の特 色が見られる貴重な建物です。 |
経堂は創建当初、足利義兼が正妻の供養の為一切 経会の道場として建てられました。 現在の経堂は 江戸時代初期(1615-1660)に建てられた桁行一間 、梁間一間、一重もこし付、宝形造、本瓦葺の建物 で内部には八角輪蔵が設置され一切経を保管して います。 もこし付経蔵の中では全国で2~3位の 規模をもっています。 |
|
 |
||
| 大雄寺 栃木県大田原市黒羽田町450 大雄寺は、応永11年(1404)に余瀬村に創建された 曹洞宗の寺院です。 後に戦乱で焼失しますが文安 5年(1448)に大関忠増によって再建され、天正4年 (1576)に大関高増の居城が余瀬白旗城から黒羽 城に移った際に現在地に移築されました。 七堂伽 藍の整った総カヤ葺の室町時代の様式を残す禅寺 です。 城南要衝の地にあり、周囲は高い土畳をめぐらし、 戦があれば黒羽城の砦の機能を備えていました。 総門左側に経蔵が建っています。 総門左右には お寺を囲むように廻廊が巡らされています。 総門を くぐると右側に鐘楼、正面に本堂が見え本堂右側に は御霊屋の入口があります。 廻廊左側に座禅堂、 右側に庫裡が建っています。 すべて江戸中期に再 建された建物です。 |
 |
 |
| 大雄寺 総門 | 大雄寺 廻廊 | |
 |
 |
 |
| 大雄寺 本堂 | 大雄寺 御霊屋 | 大雄寺 座禅堂 |
 |
 |
 |
| 大雄寺 庫裡 | 大雄寺 鐘楼 | 大雄寺 経蔵 |
 |
||
| 大前神社 栃木県大田原市黒羽田町450 大前神社は、 神護景雲年中(767~)に社殿が再建されており、1200年以上の歴史を持つ神社です。 延喜5年(905)には「延喜式」の式内社に選上されました。 平将門は乱(935)を興すに至り、大前神社に て合戦勝利の祈願をしています。 |
 |
|
| 大前神社 両部鳥居 | ||
| 享和2年(1802)に建立された鳥居です。 大前神社 参道の第3の鳥居で、高さ6.1m、屋根付、木造の 鳥居です。 |
||
 |
 |
 |
| 大前神社 拝殿 | 大前神社 本殿 | 大前神社 銅燈籠 |
| 元禄元年(1688)に建立した建物です。 三間三面、 入母屋造、千鳥破風、向拝一間軒唐破風付、銅板 葺の建物です。 |
文禄2年(1593)の再建といわれています。 三間社 入母屋造、向拝付、銅版葺の建物です。 随所に唐 獅子・龍・象・麒麟等の霊獣彫刻が施されています。 |
延天明3年(1783)の建立です。 総高3.0m、青銅 製の燈籠です。(上部がなくなっていました) |
 |
||
 |
 |
|
| 八幡宮 拝殿 栃木県下野市薬師寺1509 |
八幡宮 本殿 栃木県下野市薬師寺1509 |
|
| 薬師寺八幡宮は、貞観17年(875)清和天皇の御勅定により東北守護の大神として石清水八幡宮の御分 霊を勧請して創建されたと言われています。 本殿、拝殿とも、寛文2年(1662)に領主佐竹右京太夫により 再建されたものです。 ケヤキ-市天然記念物 |
||
 |
||
| 今宮神社 栃木県鹿沼市今宮町1692 延歴元年(782)の創立といわれています。 日光二荒山神社の分社的性格をもち、日光山鹿沼今宮権現と称していました。 天文3年(1535)日光神領惣政所の 壬生綱房が、鹿沼築城と共に現在地に遷し、今宮権現と称して城の鎮守とされました。 慶長13年(1608)、現在見られるような優美な権現作りの社殿に整備され ました。 |
||
 |
 |
 |
| 今宮神社 唐門 | 今宮神社 拝殿 | 今宮神社 本殿 |
| 嘉永2年(1849)の建立です。 参道正面の第一の 門で、左右に廻廊が接続しています。 切妻造り四 脚門で、軒唐破風をつけています。 主柱は丸柱、 控柱は角柱で銅板瓦棒葺の屋根です。 |
建設時期は本殿よりは遅れるものの、所期の権現 造りの形式をよく受け継いでいます。 桁行三間、 梁間二間の入母屋造り、向拝付、銅板瓦棒葺の建 物です。 |
延宝9年(1681)の改築です。 桁行一間、梁間一 間の一間社流造り、向拝付、銅板瓦棒葺の建物で す。 |
 |
||
| 医王寺 栃木県鹿沼市北半田1250 医王寺は真言宗豊山派の寺院です。 日光開山勝道上人により天平神護元年(765)に創建され、弘法大師 ゆかりの寺「東高野山」と呼ばれています。 約3万坪にも及ぶ広大な敷地には、金堂・唐門・弘法大師堂・客殿が建ち並んでいます。 金堂は、現在、屋根及び木部軒廻りの全面修理中でした。 |
 |
|
| 医王寺 唐門 | ||
| 唐門は宝暦3年(1753)の建立です。 医王寺境内 の中で最も豪華な建物とされ、桁行2.9m、梁間2 .7m、の四脚門で、入母屋、茅葺で、正面には唐 破風が設えられ全体が極彩色で仕上げられていま す。 細部の手法は日光東照宮の陽明門の写しとして高 名です。 |
||
 |
 |
 |
| 医王寺 大師堂 | 医王寺 講堂 | 医王寺 客殿 |
| 大師堂は貞享3年(1686)の建立です。 三間四面、 入母屋、茅葺、妻入りで正面に一間の向拝が設え られています。 壁は内外ともに朱色で塗られ、随所 に繊細な彫刻が施されています。 |
講堂は正保2年(1645)~元禄5年(1692)の建立で す。 寄棟、銅板葺(元茅葺)の桁行12間もある大 型の木造建築です。 内部は内陣、外陣、脇陣に分 かれています。 |
客殿は貞享5年(1688)の建立です。 木造平屋一 部2階建ての寄棟、銅板葺で、桁行13間の医王寺 内で最大の建物です。 内部は客間や2階部分以 外は間仕切り壁がなく、襖や板戸などで区切られ全 てを開放すると100畳以上になります。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 磯山神社 本殿 栃木県鹿沼市磯町66 |
満願寺 本堂(大御堂) 栃木県栃木市出流町288 |
一瓶塚稲荷神社 本殿 栃木県佐野市田沼1404 |
| 磯山神社は永延2年(988)の創建と伝えられる古 社です。 本殿は寛文2年(1662)に建立された三 間社流造の建物です。 建物全体が弁柄塗となっ ています。 屋根は当初檜皮葺だったのが?葺にな り、現在は銅板葺になっています。 夫婦杉-鹿沼市天然記念物 |
満願寺は天平勝宝2年(750)に開山された真言宗 智山派の寺院です。 本堂は明和元年(1764)当時に建造された、五間四 方、向拝三間、入母屋造、銅版葺の建物です。 建 物全体は弁柄漆塗で彫刻には彩色を施しています 坂東三十三観音札所第17番 山門-市文化財、出流自然林-市天然記念物 |
一瓶塚稲荷神社は文治2年(1186)に遷座された 神社です。 本殿は寛政3年(1834)の火災後に造 営された、間口2.43m、奥行4.24mの一間社、 朱塗りの権現造の建物です。 社殿・西宮神社社殿-佐野市有形文化財 |
 |
||
| 惣宗寺 栃木県佐野市金井上町2233 天慶7年(944)に 藤原秀郷が春日岡に創建したと伝えられる天台宗の寺院です。 「佐野厄除け大師」の名前で知られ、青柳大師、川越大師と共に「関東の三大師」の一つに数えられます。 徳川家康の棺が久能山から日光へ遷送される途中、元和3年(1617)春日岡山惣宗寺に一夜安置された ことから、惣宗寺の願いによって文政11年(1828)に東照宮が造営されました。 |
 |
|
| 東照宮 本殿 | ||
| 本殿は一間社、入母屋造の建物です。 正面背面 に千鳥破風、向拝の柱、梁共に龍の彫刻が施され ています。 |
||
 |
 |
 |
| 東照宮 拝殿 | 東照宮 透塀 | 東照宮 唐門 |
| 拝殿は入母屋、銅瓦棒葺、桁行3間、梁間2間、 正面1間向拝付の建物です。 内部には狩野洞 益による唐獅子が描かれています。 |
連子型 「透塀」 は、文政6年の古図とは異なり簡 略化施工されていますが、背面繰門の扉は桟唐 戸板に葵の紋章が付けられています。 |
唐門は唐様の向唐門で、銅瓦棒葺、細部には龍 や波、植物を模した彫刻が施され極彩色で彩られ ています。 |
 |
||
| 鑁阿寺 栃木県足利市家富町2220 (国指定史跡) 鑁阿寺は真言宗大日派の本山です。 源姓足利氏二代目の足利義兼(足利尊氏の7代前)が建久7年(1196)に自宅である居館に持仏堂を建て、守り本尊として 大日如来を祭ったのが始まりといわれています。 その後、三代目の足利義氏が堂塔伽藍を建立し足利一門の氏寺としました。 周囲に土塁と堀をめぐらした寺域 はほ正方形で、約4万㎡あり、鎌倉時代の武家屋敷の面影を今に伝えています。 本堂(大御堂)-国宝、鐘楼・経堂-国重要文化財、中御堂(不動堂)・智願寺殿御霊屋(蛭子堂)・宝庫・北門・水屋-市有形文化財、イチョウ-県天然記念物 |
||
 |
 |
 |
| 鑁阿寺 太鼓橋(反橋) | 鑁阿寺 楼門 | 鑁阿寺 多宝塔 |
| 太鼓橋は安政年間(1854-59)に再建された建物で す。 鑁阿寺正面入口の周溝にかけられた桁行約7 .8m、梁間約3.4mの反り橋です。 総欅の素木 造り、屋根付き、唐破風桟瓦葺、内部天井は格天井 とし、周溝の縁石に切石の橋脚を用いています。 県内ではただひとつの屋根つきの橋です。 |
楼門は永禄7年(1564)に13代将軍足利義輝が再 建したものです。 三間一戸、入母屋造、本瓦葺の 八脚門楼門で、三間一戸、入母屋、瓦葺き、2層目 には高欄が廻り、両脇には鎌倉時代運慶作といわ れる仁王像が安置されています。 |
多宝塔は元禄5年(1692)に5代将軍徳川綱吉の生 母桂昌院が寄進再建された建物です。 相輪の宝 珠は寛永6年(1629)のものです。 三間多宝塔、 銅板葺瓦棒付の建物で、多宝塔としては日本最大 級とされています。 |
 |
 |
 |
| 鑁阿寺 東門 | 鑁阿寺 西門 | 鑁阿寺 御霊屋 |
| 東門は永享4年(1432)に公文所奉行に再建された 建物です。 本瓦葺、切妻造の四脚門です。 鎌倉 時代の武家造りの剛健な風格がしのばれます。 |
西門は東門と同じく、永享4年(1432)に公文所奉行 に再建された建物です。 本瓦葺、切妻造の四脚門 です。 |
御霊屋は11代将軍徳川家斉が寄進した建物です。 正門に棟門(神門)を設け、板塀の瑞垣で囲み、そ の中に桁行5.7m梁間3.9m入母屋、銅板葺き の拝殿、その後方に桁行2.0m梁間1.3m、一 間社流造、銅瓦棒葺の本殿を配しています。 さらに本殿の周囲にも拝殿に接続して内瑞垣がめ ぐっています。 門は柱真々2.2mで、附属塀延長 は28.47mとなっています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 塩原八幡宮 本殿 栃木県那須塩原市中塩原11 |
畑下温泉神社 本殿 栃木県那須塩原市塩原443 |
峯薬師堂 栃木県那須塩原市塩野崎251 |
| 塩原八幡宮の創建は大同2年(807)と言われていま す。 けやき造り、間口1間、奥行1間、流造りの厚 板葺き屋根の建物です。 逆杉-国指定天然記念物 大栃-市指定天然記念物 |
畑下温泉神社は貞享4年(1687)創建、享保5年( 1720)に再建された、間口一間、奥行一間、権現 造、こけら葺の建物です。 |
峯薬師堂は、かつては薬王寺の本堂であったもので す。 間口三間、奥行三間の四角堂で、幅六尺の回 廊があります。 建築年代は不明です。 コウヤマキ-市天然記念物 |
 |
||
 |
 |
|
| 薬師堂 仁王門 栃木県那須塩原市塩野崎251 |
雲巌寺 山門 栃木県大田原市雲岩寺27 |
|
| 応安2年(1369)に小堂を建築し峯薬師と称しました その後、寛永9年(1632)の火災により全焼してしま ったため、それ以降の建築と思われます。 間四間 奥行三間の八脚門です。 |
雲巌寺は大治年間(1126-1131)開基された臨済宗 妙心寺派の寺院です。 天正18年(1590)の豊臣秀 吉の小田原攻めの戦火で堂宇のほとんどが焼失し ましたが、山門は奇跡的に焼失を免れました。 スギ-市指定天然記念物 |
|
 |
||
 |
 |
 |
| 泉渓寺 勅使門 栃木県那須烏山市金井1-12-5 |
太平寺 仁王門 栃木県那須烏山市滝395 |
太平寺 本堂 栃木県那須烏山市滝395 |
| 泉渓寺は延文5年(1360)に創建された曹洞宗の寺 院です。 元中2年(1385)源翁禅師は、那須野ヶ原 の殺傷石が人畜を害していた事を聞き、勅命を受け 鎮めました。 この功により後小松天皇から大寂院 の勅額を賜り、勅願所となりました。 その際、勅使 門を建立したと伝えられています。 |
太平寺は延暦22年(803)に創建された天台宗のお寺です。 境内には川口松太郎の小説「蛇姫様」で知ら れる「お六姫」の墓があります。 カヤ-市天然記念物 |
|
| 仁王門は享保10年(1725)に建てられた三間一戸 の八脚楼門で、入母屋、銅瓦葺きの建物で、外壁は 朱色に塗られ二層目には高欄が廻されています。 |
本堂は享保10年(1725)に建てられた母屋、銅瓦葺 きの建物です。 |
|
 |
||
 |
||
| 宝積寺稲荷神社 本殿 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺549 |
||
| 天保12年(1841)に建立された一間社流造、こけ ら葺、正面向拝付き、向拝部の欄間に龍、木鼻に 獅子、扉両脇に孔雀の花鳥、屋根破風に松、外壁 欄間部に花、鳥、波飛沫など精緻な彫刻が施され ている建物です。 |
||
 |
||
 |
 |
 |
| 安国寺 六角堂 栃木県下野市薬師寺1737 |
歓喜院 楼門 栃木県下都賀郡壬生町羽生田2169 |
満願寺 山門 栃木県栃木市出流町288 |
| 江戸時代には釈迦堂と呼ばれ、文化2年(1805)に 刊行された「木曽路名所図鑑」にも確認できます。 建物の形、屋根、外回りの柱、礎石までが正六角形 造りの仏堂です。 |
歓喜院は嘉応2年(1170)に開基された真言宗智 山派の寺院です。 楼門は安永9年(1780)に建造 された三間一戸、銅版葺の建物です。 |
満願寺は天平神護元年(765)に開山された真言 宗智山派の寺院です。 山門は享保20年(1735) の建立です。 一対の仁王尊像は足利時代の作。 以前は茅葺屋根でしたが昭和初年に金属板に葺 き替えられました。 坂東三十三観音札所第17番 本堂-県文化財、出流自然林-市天然記念物 |
 |
||
 |
 |
 |
| 一瓶塚稲荷神社 本殿 栃木県佐野市田沼1404 |
西宮神社 社殿 栃木県佐野市田沼1404 |
日枝神社 本殿 栃木県芳賀郡益子町七井1010 |
| 一瓶塚稲荷神社は文治2年(1186)に遷座された 神社です。 幣殿は間口4.55m、奥行き7.28m 拝殿は間口8.19m、奥行き4.55mで、天保5年 (1834)の火災後に造営された建物です。 本殿-栃木県指定有形文化財 |
一瓶塚稲荷神社の右側に祀られています。 一瓶 塚稲荷神社の再建頃の建造で、間口0.81m、奥 行き1.56mの建物です。 本殿-栃木県指定有形文化財 |
神護景雲2年(768)の創立で、矢嶋郷総鎮守として 崇められた神社です。 本殿は享保4年(1719)の建 立で花鳥の彫刻が施された江戸時代中期の様式を 伝える建物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 荒橿神社 本殿 栃木県真岡市八木岡273 |
鹿島神社 本殿 栃木県真岡市西田井1071-1 |
旧足利学校遺跡図書館 栃木県足利市昌平町2338 |
| 康永元年(1342)に勧進されたのが始まりと言わ れる神社です。 本殿は安永3年(1774)に再建さ れた間口1.5m、奥行2.7mの一間社流造茅葺 の建物です。 |
延長年間(920~930)に創建された神社です。 本 殿は享保6年(1721)に再建されたもので、一間社、 流れ造、銅板葺の建物で、細部には精巧な彫刻が 施されています。 |
大正4年(1915)に建設された、入母屋造桟瓦葺で、 基礎及び外壁はレンガ積みをした上に石材や漆喰 で仕上げた建物です。 和風の屋根、洋風の外壁、 内装など和洋折衷の特徴の見られる建物です。 |
 |
||
| 鑁阿寺 (国指定史跡) 栃木県足利市家富町2220 鑁阿寺は真言宗大日派の本山です。 源姓足利氏 二代目の足利義兼(足利尊氏の7代前)が建久7年 (1196)に自宅である居館に持仏堂を建て、守り本 尊として大日如来を祭ったのが始まりといわれてい ます。 その後、三代目の足利義氏が堂塔伽藍を建 立し足利一門の氏寺としました。 周囲に土塁と堀 をめぐらした寺域はほ正方形で、約4万㎡あり、鎌倉 時代の武家屋敷の面影を今に伝えています。 本堂(大御堂)・鐘楼・経堂-国指定重要文化財 楼門・東門・西門・多宝塔・御霊屋・太鼓橋 -県指定有形文化財 イチョウ-県指定天然記念物 |
 |
 |
| 鑁阿寺 中御堂(不動堂) | 鑁阿寺 智願寺殿御霊屋(蛭子堂) | |
| 中御堂は不動堂とも呼ばれ文禄元年(1592)に再建 された入母屋、瓦葺、一間の向拝付きの建物です。 以前は本堂と廊下で繋がっていましたが昭和44年 の改修で現在の形となりました。 右側には足利氏 が使用した800年前の古井戸の跡があります。 |
足利義兼の正妻北条時子(北条時政の娘)を祀り、 法名から智願寺殿と呼ばれ、蛭子堂とも呼ばれてい ます。 創建年は不詳で、木蔵風切妻、瓦葺、妻入 、向拝付の建物です。 |
|
 |
 |
 |
| 鑁阿寺 宝庫(大黒堂) | 鑁阿寺 北門 | 鑁阿寺 御水屋 |
| 宝庫は宝暦2年(1752)に建立された、校倉造で、屋 根は寄棟造で瓦葺の建物です。 校倉は断面が三 角形の木をはり合わせてそれぞれの山形をつくって おりのこぎりの歯のようになっています。 42世忍空 上人の代に足利家伝来の大黒天を祀ったので大黒 堂とも呼ばれています。 |
北門は弘化2年(1845)に再建されたものです。 塔 中十二坊筆頭の千手院の山門でした。 明治4年(1 871)に千手院を除く支院全てを政府に上地し、大正 7年(1918)に山門を現在地に移設しました。 薬医 門としては規模が大きく江戸時代末期の形式を有し ています。 |
御水屋は明治22年(1888)に再建された建物です。 再建時には田崎草雲がこの天井に雲竜の墨絵を描 いたとされ、現在もその跡が残されています。 江戸 末期の特徴がよく残されていて、近在の寺院の御水 屋と比べても大規模な建物です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| わたらせ渓谷鐵道第一松木川橋梁 栃木県日光市足尾町字田元 |
足尾銅山電話資料館 (旧足尾銅山電話交換所) 栃木県日光市足尾町掛水2281 |
わたらせ渓谷鐵道足尾駅本屋 及び上り線プラットホーム 栃木県日光市足尾町掛水2316 |
| 大正3年(1914)に建造されました。 渡良瀬川上 流に架かる橋長56m、単線仕様の鋼製3連桁橋 です。 橋脚は頂部まで丁寧に石貼した石積躯体 にイギリス製の錬鉄トレッスル橋脚を載せる特殊な 造りです。 |
昭和26年(1951)に建造された木造平屋建、鉄板 葺、建築面積100㎡の建物です。 足尾銅山には 明治19年に電話が架設され、国内では民間初の 私設電話となりました。 モルタル塗の外壁に縦長 窓を並べ、寄棟造の屋根を架けた外観です。 |
大正元年(1912)の建造です。 本屋は桁行20m 、梁間6.4m、木造平屋建、外装下見板張及び真 壁造、瓦葺、建築面積209㎡の建物です。 東半 分を待合室、西半分を事務室にしています。 プラットホームは延長109m、石造です。 |
 |
||
 |
 |
 |
| わたらせ渓谷鐵道足尾駅 下り線プラットホーム 栃木県日光市足尾町掛水2316 |
わたらせ渓谷鐵道足尾駅 手小荷物保管庫 栃木県日光市足尾町掛水2310 |
わたらせ渓谷鐵道足尾駅危険品庫 栃木県日光市足尾町掛水2316 |
| 大正元年(1912)の建造です。 南面を三段の間知 石布積とし、東西の各端部4.3m部分を斜路状に 築いた延長109mのプラットホームです。 |
昭和10年(1935)の建造です。 桁行2.7m、梁 間1.8m、切妻造妻入とする木造平屋建、瓦葺、 建築面積5.0㎡の建物です。 プラットホーム側に 出入口を設け、外装は押縁下見板張とし、内部に は棚等の造作を残しています。 |
大正3年(1914)の建造です。 灯油等の危険品を 収納するために造られた間口2.7m、奥行1.8m の片流、波形スレート葺の煉瓦造平屋建、建築面 積5.0㎡の建物です。 外壁は半枚厚の長手積で 、四隅に柱形をつくり、開口部は欠円アーチ形とし ています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| わたらせ渓谷鐵道足尾駅 貨物上屋及びプラットホーム 栃木県日光市足尾町掛水2309 |
足尾キリスト教会 栃木県日光市足尾町赤沢2525 |
わたらせ渓谷鐵道渋川橋梁 栃木県日光市足尾町赤沢・松原 |
| 大正元年(1912)の建造です。 三面を間知石の布 積で築いた延長24mのプラットホーム上に桁行22 m、梁間5.5m、切妻造、平側吹放ち、妻側外装下 見板張とする木造平屋建、スレート葺、建築面積17 9㎡の貨物上屋を載せています。 |
明治41年(1908)に建造された木造平屋建、鉄板 葺、建築面積119㎡の建物です。 南正面の中ほ どに玄関を設け、西側の一室を会堂とし、東側を牧 師の居住空間とする足尾で初めての本格的な教会 堂です。 |
大正元年(1912)に建造されました。 渡良瀬川水 系渋川に架かる橋長14m、単線仕様の鋼製単桁 橋です。 橋台は花崗岩をイギリス積風に積んだ造 りになっています。 |
 |
||
 |
 |
 |
| わたらせ渓谷鐵道通洞駅本屋 及びプラットホーム 栃木県日光市足尾町掛水2316 |
わたらせ渓谷鐵道通洞橋梁 栃木県日光市足尾町中才 |
わたらせ渓谷鐵道有越沢橋梁 栃木県日光市足尾町中才 |
| 大正元年(1912)の建造です。 本屋は木造平屋建 、瓦葺、建築面積159㎡の建物です。 桁行10m 、梁間6.8mの事務室と桁行6.8m、梁間7.3m の待合室をT字形に配しています。 石造103m長 のプラットホームを設けています。 |
大正元年(1912)に建造されました。 橋長13m、 単線仕様で上路式プレートガーダーを用いた鋼製 単桁橋で、桁両側面に銘板を付け、橋台は花崗岩 をフランス積風に積んでいます。 |
大正元年(1912)に建造されました。 渡良瀬川水 系有越沢に架かる橋長14m、単線仕様の鋼製単 桁橋です。 橋台は花崗岩をイギリス積風に精緻に 積んでいます。 |
 |
||
 |
||
| わたらせ渓谷鐵道第二渡良瀬川橋梁 栃木県日光市足尾町遠下・小ナギ |
||
| 大正元年(1912)に建造されました。 渡良瀬川に 架かる橋長95m、単線仕様の鋼製2連橋梁です。 橋台及び橋脚付。 |
||
 |
||
| 織姫神社 栃木県足利市西宮町3889 足利市は古くから織物を中心に栄えてきました。 和銅6年(713)には足利織物が文献上に残っています。 1300年の伝統と歴史をもつ足利織物の守り神として奉られているのが織姫神社です。 宝永2年(1705)に 創建され、のちに通4丁目の八雲神社の境内社として祀られました。 明治12年(1879)に織姫山に遷座さ れましたが、明治13年のに火災によって焼失してしまいました。 この後、仮宮のままでしたが昭和12年(1 937)に平等院鳳凰堂をモデルとして現在の社殿が完成しました。 |
 |
|
| 織姫神社 社殿 | ||
| 両崖山南斜面の中腹に築かれた石積基壇上に、昭 和12年(1937)に建立された、鉄筋コンクリート造平 屋建、銅板葺、建築面積140㎡、本殿透塀折曲り 延長29m付の建物です。 正面中央に入母屋造、 千鳥破風付きの拝殿を置き、その両側に神輿舎と 神饌所、背後に幣殿と切妻造の本殿を配していま す。 垂木より上を木造とした鉄筋コンクリート造神 社建築です。 |
||
 |
 |
 |
| 織姫神社 神楽殿 | 織姫神社 社務所 | 織姫神社 手水舎 |
| 昭和12年(1937)に建立された、桁行6.2m、梁間 3.8m、東西棟、入母屋造、銅板葺の木造平屋建、 建築面積24㎡の建物です。 |
昭和12年(1937)に建立された、桁行6間半の入母 屋造、銅板葺、木造平屋建一部地階付、建築面積1 02㎡の建物です。 神楽殿と渡廊で繋がっています |
昭和12年(1937)に建立された、桁行1.97m、梁 間0.7m、切妻造、銅板葺、鉄筋コンクリート造平屋 建、建築面積1.4㎡の建物です。 垂木以上を木造 としています。 |